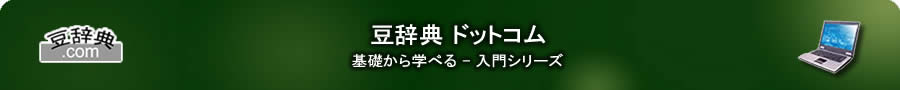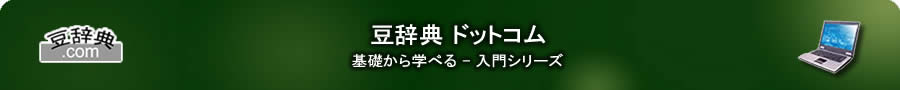デジカメ とは
 フィルムを必要としないカメラがデジタル・カメラ (デジカメ) である。もう少し補足すると レンズと絞り、そして、シャッターを通って フィルムの役割をする撮像素子に到達する光から画像を得る機器である。デジカメは 1990年後半頃から消費者向けに市販され始めたが、その後、性能と価格の両面で急速な進化を遂げた。フィルム不要で高画質、かつ、現像せずに PC などで その高画質な画像を簡単に見ることが出来るデジカメの利便性もあり、2005年頃までには フィルム式の 所謂 銀塩カメラを買う人は殆ど居なくなった。 フィルムを必要としないカメラがデジタル・カメラ (デジカメ) である。もう少し補足すると レンズと絞り、そして、シャッターを通って フィルムの役割をする撮像素子に到達する光から画像を得る機器である。デジカメは 1990年後半頃から消費者向けに市販され始めたが、その後、性能と価格の両面で急速な進化を遂げた。フィルム不要で高画質、かつ、現像せずに PC などで その高画質な画像を簡単に見ることが出来るデジカメの利便性もあり、2005年頃までには フィルム式の 所謂 銀塩カメラを買う人は殆ど居なくなった。
また、最近のデジカメは動画も撮ることの出来るものが主流になってきた。フィルムが不要だから 取敢えず シャッターを押して写真や動画を撮っても 一銭もかからないのがデジカメの良さだ。また、SD メモリー・カードの容量アップと価格低下が進み、近年では 8GB でも 1000円程度から購入可能になっており、高画質の写真を数百枚、場合によっては、それ以上 1枚のメモリー・カードに撮ることが出来るようになった。従って、旅行などで どれだけ写真や動画を撮ることができるかという観点からの ボトルネックは電池 (スペアの電池は 数千円と比較的高価) になった。
価格に関係なく、どのような製品でも 便利な全自動 (オート) の機能が付いているから 写真の知識がなくとも ダイヤルを オートに合わせて 何枚か撮れば そこそこの写真が撮れる。さらに、ほんの少し高級なカメラを買えば かなり芸術的な写真も撮れる機能が付いてくるから 驚きだ。誰でも、一端の写真家になった気になれるのである。
かつては高価だった一眼レフの価格も えっ と思うような値段まで下がったので、それなら自分も一眼レフを と考えている人も少なくないだろう。しかし、一眼レフを買う (自分にとっての) 理由は何なのか、そして、本当に一眼レフのカメラを買う価値があるのかという疑問を持ったり、一眼レフ以外の選択肢は何があるのか、などと言った疑問を持っている人も居るだろう。そこで、ここでは (a) デジカメの種類と特徴、(b) 写真撮影の基礎知識と基本テクニック について 以下のとおり 分かり易く解説する。
(a) デジカメの種類と特徴
デジタル・カメラの種類については 色々な分類方法があろうが、特殊なカメラは別にして、以下のように分類すれば、その特徴や違いを理解する上で便利である。即ち、(1) 一眼レフ、(2) ミラーレス一眼、(3) ネオ一眼、(4) コンデジ といった分類である。
|
|
|
|
(1) 一眼レフ |
(2) ミラーレス一眼 |
(3) ネオ一眼 |
(4) コンデジ |
勿論、カメラによって デザイン、機能、性能、価格はまちまちで、簡単に それらの違いを一纏めにして分かり易く、しかも、間違いなく説明することは難しいが、大雑把に これら四種類のカメラの特徴を 一覧表形式にして比較すると 以下のようになる。
デジカメの種類 |
ビューファインダー |
レンズ交換 |
撮像素子 |
大きさ |
価格 |
| (1) 一眼レフ |
有 |
可 |
極大/大 |
極大/大 |
極高/高/中 |
| (2) ミラーレス一眼 |
無 |
可 |
大/中 |
中 |
高/中 |
| (3) ネオ一眼 |
有 |
不可 |
小 |
大/中 |
中 |
| (4) コンデジ |
無 |
不可 |
小 |
中/小 |
低/中 |
(1) 撮りたい写真に応じてレンズを交換でき、高機能で最もハイレベルな写真を撮ることの出来るのが一眼レフの魅力である。近年は 一眼レフでも レンズが付いて 5万円程度の安価なものも売られており、手軽にハイレベルな撮影技術を駆使した写真が撮れるようになった。とは言え、写真機本体だけでなく、交換レンズも高価なものが多いから これにハマると 比較的 出費がかさむのが難点だ。また、写真撮影の知識や技術を ある程度身につけなければ、宝の持ち腐れになってしまうような機能や性能を有したカメラであるとも言え、写真撮影の知識や技術なしに ある程度の写真を撮ることが出来れば良いと考えている人には 不向きなものである。
(2) ミラーレス一眼と呼ばれる新しいジャンルのデジカメが最近は人気になっているが、毎日持ち歩いても気にならないサイズで、一眼レフに近い画質と撮影テクニックが楽しめるという点が最大の売りだ。機能的にも、一眼レフの機能を数多く有するし、画質も一眼レフに近いものが得られるが、ファインダービューがないこと、そして、小さなボディーについた限られた数の操作ボタンで多くの機能が使えるようにしていることで、操作に時間がかかったり、やや操作し難いことなどが難点だと言えよう。
(3) コンデジの一ジャンルとも言えるが、ネオ一眼は、比較的 高価な (開放値の明るい) ズームレンズが装着されており、一眼レフのカメラを操作する感覚で ビューファインダーから被写体を見て シャッターを切ることが出来るのが魅力だ。操作も分かり易く、し易いモデルが多く、何と言っても 価格が手頃である。ただし、画質に大きな影響を及ぼす撮像素子が 通常はコンデジ並みと小さいこと、レンズの交換が出来ないことなどがマイナス要素である。
(4) コンデジの魅力は、大きさと価格である。小さなものは胸のポケットに入る大きさだから、気楽に持ち運ぶことが出来る。上位機種と下位機種の差はあるだろうが、機能的に、また、画質においては、言うまでもなく、上述のカメラとは比較にならない。とは言え、最近のコンデジは、かなりの多機能、高機能 (手振れ軽減、高 ISO 機能、逆光対応機能、顔検知、動画など) のものが多くなっているから、数年前のモデルと比べれば、格段に優れたカメラになっている。最近では画素数を気にしてカメラを比べるようなことは殆どなくなった。
(b) 写真撮影の基礎知識と基本テクニック
まず始めに 覚えるべき基本だが、綺麗な写真を撮るには その光の総量、即ち、露出を適度にコントロールする必要があると言うことだ。露出オーバー (過多) であれば 写真が白っぽくなってしまうし、露出アンダーであれば 黒っぽい写真になる。カメラの露出、即ち、撮像素子が受ける光の量は レンズの明るさ (詳細後述) と絞り、及び、シャッターの開放時間 (シャッター・スピード) の組み合わせでコントロールする。適度な露出になるシャッター・スピードと絞りの組み合わせは 何通りもあるが、カメラの設定を自動 (AUTO)やシーン (SCN) でポートレートや風景、夜景などにすれば (詳細後述) その組み合わせはカメラが自動的に決める仕組みである。
レンズの明るさとは 絞りを開放にした時に入る光の量のことで、それは開放時の レンズの直径によって決まる F値という数値で表わされる。入る光の量は レンズの面積に比例して 増減するから、F値が 1.4倍 (正確には ルート 2倍) になると光の量は 1/2 になるというルールで、F 1.4 のレンズは、F 2.8 のレンズの約 4倍の量の光を取り込むことが出来るという理屈だ。F値は 1.4、2.0、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32 などと設定されるようになっているが、これは数字が大きくなる毎に光の量が半分になっていくことを意味する。
シャッター・スピードが 1秒より短い場合は通常分子が 1の分数で表記されるが、シャッター・スピードは 1/25 より 1/50 の方が 2倍早く 光の量は 1/2 になる。一方、レンズの明るさと レンズの絞りは F値で表示されるが、レンズの直径が大きく、絞りが開いていれば光の量は増え、その量はその面積に比例する。つまり、絞りの直径 (即ち、F値) がルート 2倍になれば、絞りの面積は 2倍になり、光の量も 2倍になる。
つまり、1/125 で F 8 の設定と 1/500 で F 4 の設定では同じ量の光が得られることになる。当然ながら、どの組み合わせを選んだかは最終的な仕上がりに影響するが、シャッタースピードと絞り (F値) の組み合わせは、動きのある物 (例えば、噴水) を写す時や背景のぼかしを入れたい時 (詳細後述) などに影響を与えるファクターである。
 明るいレンズは暗い所で シャッター・スピードを遅くせずに撮影することも出来るし、被写界深度 (詳細後述) を浅くすることもできるので 一眼のカメラで写真を撮れば 右のような背景を ぼかした写真を撮ることも可能になるが、コンデジでは そうした設定の融通が利かないという差がある。望遠で (焦点距離の長い) 明るいレンズを用い、絞りを開放し、シャッター・スピードを速くすると (その逆の設定に対して) 焦点を合わせた被写体以外の画像は (焦点がまったく合っていない状態になり) ボケて写るという現象が見られる。背景をぼかして被写体 (例えば、人物、動物、虫、花など) を浮かび上がらせるという手法だが、色々なレンズを使って露出の設定を自由に変えられる一眼ならではの撮影テクニックと言える。 明るいレンズは暗い所で シャッター・スピードを遅くせずに撮影することも出来るし、被写界深度 (詳細後述) を浅くすることもできるので 一眼のカメラで写真を撮れば 右のような背景を ぼかした写真を撮ることも可能になるが、コンデジでは そうした設定の融通が利かないという差がある。望遠で (焦点距離の長い) 明るいレンズを用い、絞りを開放し、シャッター・スピードを速くすると (その逆の設定に対して) 焦点を合わせた被写体以外の画像は (焦点がまったく合っていない状態になり) ボケて写るという現象が見られる。背景をぼかして被写体 (例えば、人物、動物、虫、花など) を浮かび上がらせるという手法だが、色々なレンズを使って露出の設定を自由に変えられる一眼ならではの撮影テクニックと言える。
ところで、被写界深度とは焦点の前後にある対象物にピントがあっているように見える範囲のことである。つまり、被写界深度が浅ければ、焦点を合わせたもの以外は、ぼけて写る訳だが、それは、長焦点レンズ(望遠レンズ)を使用し、絞りを開いて近距離に焦点を合わせれば得ることの出来るものである。逆に、短焦点レンズ (広角レンズ) を使用し、絞りこんで (F値を大きくして) 遠距離に焦点を合わせれば、広範囲のものに焦点が合った写真が撮れる。ピンホールのように 非常に小さい絞りを使うと 極めて広範囲にピントを合わせることができるが、それをパンフォーカスと呼ぶ。
ズームレンズは 被写体を見ながら レンズの倍率を自由に変えて望ましいレイアウトの画像を撮影することができる利便性がある一方、レンズの開放 F値が 大きくなってしまうので、そうした制限が出るというデメリットもある。例えば、比較的安価な一眼レフのカメラに付いてくる 18mm - 55mm のズームレンズの F値は 3.5 - 5.6 といった具合だ。つまり、ある程度背景をぼかした写真は撮れるが、50mm/F1.8 のような (比較的 低価格の) レンズを使って撮った写真との間でも そのボケ具合には 大きな差が出ることになる。
 さて、暗いところでの撮影は、既に説明したように、F値が大きくなればなるほど シャッター・スピードを遅くする必要が生じるが、そうなれば シャッターが開いている間に カメラ、もしくは、被写体が動けば ピンボケの写真になるという問題が生じる。そこで光量が不足している場合は ISO 感度を上げて、シャッター・スピードをあまり遅くしないで撮影するという技術の応用がなされる。しかし、ISO 感度を上げると画像が荒れるという問題があり、そうした技術の応用にも限界があった。ところが、近年は そうした画像の荒れを軽減する技術 (ノイズ・リダクション) や手振れ補正の技術などが進んだこともあり、夜景を普通のズームレンズで三脚を使わずに (ISO = 3200 や 6400 のようなレベルで) 比較的 綺麗に写せるような製品が多く出現している。 さて、暗いところでの撮影は、既に説明したように、F値が大きくなればなるほど シャッター・スピードを遅くする必要が生じるが、そうなれば シャッターが開いている間に カメラ、もしくは、被写体が動けば ピンボケの写真になるという問題が生じる。そこで光量が不足している場合は ISO 感度を上げて、シャッター・スピードをあまり遅くしないで撮影するという技術の応用がなされる。しかし、ISO 感度を上げると画像が荒れるという問題があり、そうした技術の応用にも限界があった。ところが、近年は そうした画像の荒れを軽減する技術 (ノイズ・リダクション) や手振れ補正の技術などが進んだこともあり、夜景を普通のズームレンズで三脚を使わずに (ISO = 3200 や 6400 のようなレベルで) 比較的 綺麗に写せるような製品が多く出現している。
 また、逆光の場合は 被写体には光が直接当たらないにも拘らず その背景は極めて明るい訳だから、通常は 被写体が黒っぽくなってしまう訳で 望むような写真が撮れないことになる。しかし、最近のデジカメの中には 複数枚の写真を異なった露出で撮影し、それらを合成して (右の写真のように) より見易い写真にするというような機能を持った製品も手頃な価格で購入出来るようになっている。 また、逆光の場合は 被写体には光が直接当たらないにも拘らず その背景は極めて明るい訳だから、通常は 被写体が黒っぽくなってしまう訳で 望むような写真が撮れないことになる。しかし、最近のデジカメの中には 複数枚の写真を異なった露出で撮影し、それらを合成して (右の写真のように) より見易い写真にするというような機能を持った製品も手頃な価格で購入出来るようになっている。
一方、被写体を鮮明な画像として映し出すためには カメラと被写体の距離に応じてレンズの焦点を合わせる必要があるが、その操作も 最近のカメラは (その性能に違いはあるが) 瞬時にして自動的にやってくれるので、写真はただカメラの設定を AUTO または SCN から 適当なモードを選び、被写体にカメラを向け、シャッター・ボタンを半押しにし (ピントを合わせ) てから、シャッターを切れば写真が取れる仕組みになっている。焦点を合わせる オートフォーカス機能の性能、即ち、そのスピードや精度、そして、メカニズムはカメラによって異なるが そうした操作をカメラが自動的にやってくれることで、カメラマンは被写体を観察して構図を考えたり、シャッター・シーンを逃さないようにすること、また、他の必要なカメラの操作に その能力を使うことが出来るというメリットがある。例えば、顔を検知して焦点を合わせるような、さらには、笑った時の顔を検地してシャッターを押してくれるような便利な機能も採用さるようになっている。
以上が 写真撮影の基礎知識と最近のデジカメの技術的な特徴であるが、マスターすべき基本テクニックは、以上のような最新のデジカメの機能や性能を十分に理解して、それを写真撮影の時に正しく応用すると言うことである。つまり、状況に応じて、どんな撮影モードで どのような特殊機能を どう設定して撮影すれば良いのかを シャッター・チャンスを逃さずに判断し、操作出来る能力が望まれる訳だ。
残りのコンテンツは、現在 作成中
|